
2020/09/08 環境科学科
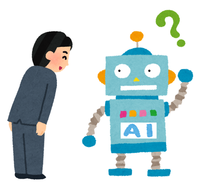
人や動物など、自然が産みだした知能を自然知能と言いますが、この自然知能をコンピュータ上で実現することを人工知能(AI:Artificial Intelligence)と言います。1950年代から現在まで、数多くの研究者によってこの「AI」の研究が進められてきていますが、ではこのAI、現在、どこまで人や動物の知能に近づいたのでしょうか?人の知能と同じように、判断や意味の理解はどこまで可能になったのでしょうか?
「AIビジネス最前線(大日本印刷株式会社,2016)」という書籍に、AIの知能に関するこんな記事がありました。皆さん、「常識」という言葉をご存じかと思います。広辞苑によると、「普通、一般人が持ち、または持っているべき知識。」という意味だそうですが、人間は、学校や社会などの共同生活経験の中で様々な「常識」を修得しています。一方、AIにとって、そのような社会経験はないため「常識」の判断は、人間以上に難しいと言われています。例えば、「お辞儀」。人間は、「お辞儀」に込められる特別な意味を社会経験から学んでいるため、相手や場所、シチュエーション、感情によって、自然に対応を変えることができます。「散歩して近所の人とすれ違ったとき」、「久しぶりに故郷の恩師を訪問したとき」、「申し訳なく謝るとき」、人間は頭を下げる動作、いわゆる「お辞儀」をするかと思います。しかし、AIには社会経験がありませんので、社会経験の代わりに、お辞儀をされた際の判断基準として「ルール」を設定します。例えば、「散歩時に近所の人にお辞儀をされた場合、お辞儀を返す」などのように設定することになるのですが、相手や場所、感情などの膨大な状況情報から、対応するヒューリスティック(経験則)な行動を1つずつプログラムしなければなりません。また、このような「お辞儀」だけをするようなお辞儀AIの実現は可能かもしれませんが、人間のように周囲の状況を総合的に判断し「自発的にお辞儀ができるAI」を実現しようとした場合は、もっと複雑な判断基準が必要となるでしょう。「お辞儀」一つ考えても、AIが人間の脳のように適切な応対ができるようになるには、まだまだ革新的な研究が必要であること実感させられますね。
さて、次回9月27日(日)のオープンキャンパスでは、「AIはイルカの顔も判定できる?!」と題して、AIの顔認証学習プロセスやその技術についての体験セミナーを開催します。動物や植物の他にも、コンピュータやAI、地理情報に興味のある高校生・ご家族の皆さん、是非ご来場下さい。
環境科学科教員 薄井智貴